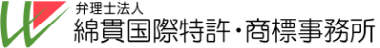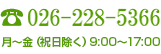特許実務雑感85
グローバル化の話の続きですが、普段の実務で痛感するのは、言語の相違による翻訳技術が適正か否かである。折角日本では比較的広い範囲で権利化できたとしても外国語に翻訳された途端に記載不備を指摘され、明確性を欠いているなどと指摘され補正をせざるを得ない場合があります。例えば他国審査官に「一体に組み付けられている」という表現と単に「組み付けられている」という表現はどのように違うのか?と問われるなど屁理屈と思われる理由が記載され、忸怩たる思いをすることがある。一体なら同時に動作しますが単に組み付けられているなら個別に動作する場合も含むのでは?と思いますが…。また、記載要件で、物の発明と方法発明を併記するといずれか一を選択しなさいと要求されたり、独立クレームは物と方法で1つのみであるとの指摘を受けたりすることもある。残念ながら、明細書作成者と翻訳者の発明理解度には隔たりがあり、意図する表現となっていない場合が多々あるのが現状と思われる。我々には少々耳の痛い話であるが、良い明細書の書き手が良い翻訳者であることが、時代が求める実務者像ではないだろうか。ただし、近い将来、AI技術の進歩等により翻訳技術の飛躍的向上が見込まれ、ソウトウェアにより自動翻訳できる時代となる可能性は十分にあると思われる。そうなると、我々代理人に求められるのは、情報を整理して何を権利化して何を権利化しないか判断したり、クライアントと共に課題を洗い出して課題解決するために真に必要な技術思想を見定めて権利化したり、権利活用を促したりする総合的なコンサルタント力が一層求められるのではないだろうか?出願件数が減少する今日ではOJTが不足する弁理士も散見されるため、より一層の精進が求められる。
弁理士 平井 善博