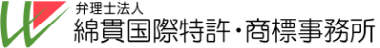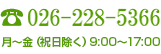特許実務雑感88
複数の部品aを当初の形態Pから異なる形態Qに変形させてから互いに組み合わせて完成品Aが組み立てられる、という発明Xにおいて部品aが形態Pから形態Qに変形することに特徴がある場合、発明Xを方法の発明として権利化する場合には、当初の形態Pを有する部品aを製造する工程、部品aを当初の形態Pから異なる形態Qへ変形させる工程、形態Qに変形させた部品aを互いに組み合わせて完成品Aを製造する工程、などのように、プロセス中に変化する部品aの形態を反映し易いため、表現にさほど苦労はしないと思われる。しかしながら、発明Xを物の発明として権利取得を希望した場合、完成品Aを構成する部品aは当初の形態Pとは異なる形態Qをしており、形態Qを有する部品aを複数組み合わせてなる完成品A、と特定しても技術的特徴は把握し難いと思われます。当初の形態Pを有する部品aは中間生成物に相当するからです。このような場合でも、部品aの特徴として形態変化を含めた特定を行なえば、権利化できる可能性があります。即ち、当初形態Pから異なる形態Qに変形可能な部品aを複数備え、形態Qを有する部品aを組み合わせてなる完成品A、のように部品aの特徴として含めることで権利化できる場合があります。物の発明において、可能な限り方法的記載は避けた方がよいですが、それ以外に物としての特徴を説明できないのであれば、方法的記載が禁じられていない以上、これを使って特定するのもやむをえません。これと似たようなケースで、構造的には類似の引用例があっても、動作が異なるため、作用効果が著しく異なる場合には、特許請求の範囲に構造の特定だけではなく、構造に基づいた動作を記載することも有効です。
弁理士 平井 善博