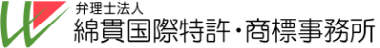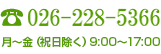知財Q&Aコーナー(85)
Q:特許法の「審判」について教えて下さい
A:「審判」は行政処分に対する不服申立ての一手段として設けられており、例えば、特許法では次のものがあります。
①拒絶査定不服審判
特許庁に出願された特許出願については、出願審査請求が行われることによって審査官が審査を開始します。審査の結果、出願が拒絶査定となった場合に、不服を申し立てる審判(拒絶査定不服審判)を請求することができます。その場合、審判官(合議体)が審理を行います。(ただし、審判過程における手続促進等を目的として、審査を行った審査官が引き続き審査を行う「前置審査」という制度も設けられています。)
②特許無効審判
特許になった発明に、本来特許されるべきではない無効理由が包含されている場合に、特許を無効にする(すなわち、権利を消滅させる)審判(特許無効審判)を請求することができます。
③存続期間延長登録無効審判
所定の条件に該当する場合、権利の存続期間が延長されますが、本来延長されるべきでないものであった場合に、延長を無効にする審判(存続期間延長登録無効審判)を請求することができます。
④訂正審判
無効審判を請求された場合の対抗手段等として設けられており、特許権の内容を訂正する審判(訂正審判)を請求することができます。
実際の請求頻度が高いのは、①の拒絶査定に対する審判ですが、必ずしも、査定を覆すことができる訳ではありません。
ちなみに、審判の結果(審決)に対する不服申立ては、知的財産高等裁判所への訴訟提起となります。
弁理士 岡村 隆志