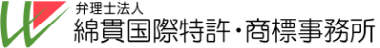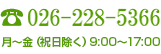特許実務雑感87
前回の続きになりますが、物の発明として記載するか方法の発明として記載するかに関する話です。あるクライアントさんから依頼を受けた発明で、部品Bの組み立てにはある治具Aを使うのだが最終製品Cには残っていない物の発明があり、これを物の発明と方法の発明の双方として記載すると仮定します。この場合、物の発明として最終製品Cに治具Aは残っていないためこれを構成要件とすることはできず、組み立てに治具Aを用いるが最終製品Cには残っていないことを特徴とする、と書きたいところです。しかしながら、ある発明Cに部材Aが残っていないことを記載しても発明Cの構成を特定したことにはならず、明確性に関する記載要件違反の拒絶理由が通知される可能性が高いです。このような場合に、思いつくのはプロダクトバイプロセスクレームですが、物同一説を採用する日本の特許法では、物の発明のプロセス部分の記述は構成としては無視されるため、完成品の構造を特定する必要があります。もちろん方法の発明としては、治具Aを用いて部品Bを組み立てる工程として特徴記載が容易に行えますが…。もっとも、複数ある部材名よりある部材を除くと指定するのは、必ずしも発明の構成が不明確になるとは言えず、むしろ従来技術との差異が明確になるケースはあります。材料や化学系のように一次元的な発明もあれば、電気回路のように二次元的な発明もあり、機械装置のように三次元的な発明もあります。これらにも物の発明、方法の発明、物を製造する方法の発明とカテゴリーが異なる発明が存在する。これらをクライアントさんの意向や業務形態を考慮して限られた時間のなかで的確に表現するには、多くの実務経験と不断の努力が必要と思われる。
弁理士 平井 善博